かつやくする微生物

微生物・活性汚泥って何?
微生物
肉眼では見ることができないくらい小さな生物(細菌や原生動物、後生動物など)のことです。大きさは、細菌は1,000分の1ミリメートル、原生動物は1ミリメートル〜100分の1ミリメートル、後生動物は1ミリメートル〜10分の1ミリメートル程度です。また、細菌や原生動物は1つの細胞だけ活動している単細胞動物ですが、後生動物はたくさんの細胞が集まってできている多細胞動物です。
活性汚泥
水を容器に入れ、空気を吹き込んで数日間そのままにしておきます。そして空気を止めると、初めに見られなかった綿状の小さいかたまり(フロック)が集まってだんだん大きくなって沈んでいきます。お椀に入ったみそ汁が雲のようにだんだんしずんでいく様子と似ています。これを活性汚泥といいます。
活性汚泥を顕微鏡で見ると様々な生物が動き回っているのがわかります。細菌が凝集したもの(細菌がお互いに集まってくっつくような物質を出して形成されます)をフロックといいます。原生動物や後世動物は、フロックを食べて量を減らし沈みやすくしたり、細菌を食べて汚れた水をきれいにするはたらきをしています。
難しい言葉ですが、活性汚泥を生物学の立場から定義すると、「細菌類や菌類を主な構成生物とし、原生動物や小形の後世動物を従属生物群とした複合生物群で、水中の有機物を吸着、分解ししながら呼吸、増殖を続ける一つの生態系」というような表現になるそうです。
また、終末処理場では活性汚泥中の微生物を観察しています。活性汚泥中の微生物の種類や量(生物相)によって、汚れた水がどれくらいきれいになっているかが分かるからです。生物相に変化が出た場合は、空気を吹き込む時間や活性汚泥を再利用する量を調整して、水質の安定に努めています。
微生物はどこからきたの?
もともと微生物は自然界に存在しています。土の中や川の水に生息していたり、胞子の形で空気中を飛んでいるものもいます。
台所などの排水にも含まれていることがあります。これらが下水の中に入り込み下水中のよごれなどを餌として増殖し、フロックを形成し、活性汚泥が出来上がります。
このように自然に微生物が増えて活性汚泥も出来上がるのですが、終末処理場に流入する下水の量が少なかったり水温が低いと安定した活性汚泥になりません。このような場合は他の終末処理場から活性汚泥を運んできます。一戸町公共下水道終末処理場でも、活性汚泥を安定させるため、奥中山の下水処理場から活性汚泥を運んできました。
微生物はどうやって増えるの?
細菌や原生動物の多くは細胞分裂(生物の体が横か縦に分かれて分裂)によって増えていきます。原生動物のなかには、体から芽が出るように増えるものや卵を産んで増えるものもあります。
どんな微生物がいるの?
活性汚泥中にはとても多くの種類の微生物が活動しています。
ここでは一戸町公共下水道終末処理場で実際に撮影した微生物を紹介します。

ボルティケラ

アルケラ

コルピディウム

ロタリア

ディプロガスター
水がきれいになるまでの時間は?
し渣分離機・・・数秒程度
オキシデーションディッチ・・・24時間から48時間程度
最終沈殿池・・・17時間程度
塩素混和池・・・1時間程度
(注)設計に基づく数値
川や海を汚さないためには?
家庭で使った水を直接川や海に流さないことです。下水道や浄化槽に流せばきれいな水になって川や海に戻っていきます。
また下水道や浄化槽に流す水もできるだけきれいな状態で流す必要があります。ですから生ごみや油などは絶対に流さないことや、洗剤などを使う場合は必要最小限の量にとどめることが重要です。
ひとりひとりの小さなこころがけで水はきれいになります。そして、川や海に戻ったきれいな水は、蒸発し雲となり雨を降らせて、また私たちが使う水となって還ってきます。
きれいな水サイクルになるように気をつけましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 下水道係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4852
メールでのお問い合わせはこちら
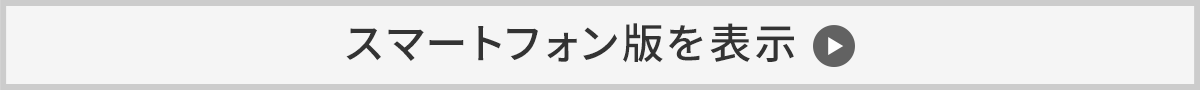






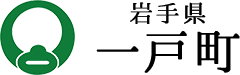
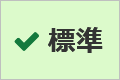




更新日:2020年03月16日