鳥獣被害対策に関する記事 全12回
概要
- 二戸農林水産振興協議会では、鳥獣被害対策に係る機運醸成を図ることを目的に、一戸町のホームページに鳥獣被害対策に関する記事を掲載し、多くの皆様に周知することとしています。
- 記事の執筆者は農研機構 畜産研究部門 動物行動管理研究領域の堂山宗一郎氏で、全12回の構成になります。
第1回 まずは相手の正体を知ろう。イノシシ・シカ対策の第一歩(農研機構 畜産研究部門 動物行動管理研究領域 堂山宗一郎氏)
皆さま、初めまして。堂山と申します。私はイノシシやシカの行動を調べ、それを元にした被害対策の手法や技術に関する研究をしています。数年前まではイノシシ被害が30年以上前から発生する西日本の中国地方を中心に仕事をしていましたが、縁あって岩手県のイノシシやシカ対策にも関わることになりました。
全国的にイノシシとシカによる農作物被害が問題になっています。一方で上手に対策をして、被害を軽減またはゼロにしている地域もあります。このような地域では、闇雲に対策をするのではなく、まずは相手となる動物のことを皆で勉強し、その正体を知った上で対策をしています。この連載では、イノシシやシカがどういう生き物なのかを皆さんに知っていただき、それを踏まえた効果的な対策をご紹介します。
手始めに、イノシシの学習能力がどのくらいかご存知でしょうか?私はイノシシを10頭ほど飼育していました。そのイノシシ達にいくつかの学習能力テストを受けてもらったことがあります。その結果、類似のテストが行われたウシやウマ、イヌとイノシシの成績はほぼ同じでした。動物の種類によって得意不得意はありますが、皆さんの家のイヌとイノシシは同程度のことをこなせる生き物だと思ってください。ちなみに私が飼っていたイノシシは、お座りの芸を10分もかからずにできるようになりました。高い学習能力は被害拡大の要因にもなりますが、それを逆手に取れば被害を止める有効な対策にもつながります。
(写真) お座りの芸をするイノシシ

第2回 あなたの近くにもイノシシが!?潜み場所が拡大中
無骨で怖そうな見た目のイノシシですが、実は非常に臆病な性格で警戒心も強い動物です。シカやクマと比べても、はるかに警戒心が強いと感じます。臆病で怖がりのイノシシが、なぜ人間が活動する田畑へ出没するようになったのでしょうか?
1番の原因は、イノシシが安全と感じ、落ち着ける場所が増えてきたことです。イノシシが落ち着いて行動できる場所は「体を隠せる場所」です。草丈の高いヤブになった場所は、イノシシが体を隠せる絶好の潜み場となります。そして近年は、耕作放棄地に草が生い茂り、イノシシの隠れ場所がさらに拡大しています。
ヤブから草丈の低い開けた場所へ出てくるイノシシを調べたことがあります。多くのイノシシがヤブと開けた場所との境界で立ち止まり、尻尾を立てる警戒行動をとりながら周囲を見回して安全確認をするという行動を見せました。その後も開けた場所へはあまり出ず、ヤブとの境界付近で活動していました。イノシシにとって開けた場所での活動は、とても苦手なことなのです。
田畑の周りにイノシシの潜める場所があれば、イノシシをどんどん引き寄せることになり、せっかく設置した電気柵も効果が薄くなってしまいます。まずは、皆さんの田畑周辺にイノシシが隠れていそうなヤブがないかチェックしてください。もしそのようなヤブがあれば、少しキレイにしてみませんか。それだけでもイノシシの行動を変えることができ、被害を減らすことに繋がります。
(写真) イノシシの痕跡がたくさんある耕作放棄地

第3回 電気柵の最重要ポイントは柵線の高さ!
被害対策として電気柵を設置している人も多いのではないでしょうか。電気柵は高い侵入防止効果があります。しかし、「適切に」設置しなければ効果がなくなってしまいます。今回は電気柵の最重要ポイントである電気柵の線(柵線)の高さや間隔について紹介します。
電気柵は、柵線に触れた動物の体に電気が流れ、発生した電気ショックによって痛みや衝撃が伝わることで侵入防止効果を発揮します。しかし、体毛の上からでは電気が通りにくく、ショックも弱くなってしまいます。強い電気ショックを与えるためには、毛の生えていない鼻先で柵線に触れてもらわなければなりません。鼻先で触ってくれるのか?と不安になるかもしれません。これは幸い、イノシシやシカは、見慣れないものや怪しいものに対して鼻先で触ってチェックするという行動の特性があり、細い柵線でも鼻先で触ってくれます。
ただし、柵線の高さや間隔を間違うと途端に鼻先で触らなくなるため、特段の注意を払って設置してください。イノシシに対応した2段の電気柵の場合、柵線を地面から20cmと40cmの高さ(20cm間隔)にしてください。この高さはイノシシが鼻先で触りやすいことが、科学的な検証により分かっています。柵を高くしたいため、30cm間隔にする方もいます。しかし、間隔が10cm広くなるだけでイノシシの行動は大きく変わり、鼻先で触らずに侵入します。高さが心配な場合は、20cm間隔の3段張り(20・40・60センチメートル)をお勧めします。
(写真)20cm間隔で適切に設置されたイノシシ用電気柵

第4回 舗装道路際の電気柵は効果なし!
前回は、イノシシに有効な電気柵を紹介しましたが、シカの場合は少し変わります。シカだけが出る場所では、地面から30・60・90・120・150cm、シカとイノシシ両方の場合は、地面から20・40・60・90・120・150cmの高さに柵線を張ることをお勧めします。シカが、どの高さを鼻先で触るか調べたところ、地面から60cmまでの線をよく触ることがわかりました。シカの場合でも柵線の間隔が広くならないように注意してください。
イノシシとシカどちらの場合でも、電気柵はアスファルトなどで舗装された場所の際から離して、土の地面に設置してください。動物に電気ショックを与えるためには、鼻先に入った電気が身体を通り抜けて足先から地面に抜けることが重要です。しかし、足が舗装された場所の上にあると電気が抜けにくく、電気ショックの威力が極端に弱くなります。足先を土の上にするためには、イノシシで柵の外側40cm以上、シカで60cm以上は土の地面になるように設置してください。
電気柵を夜だけ通電するモードで使うことはお勧めできません。イノシシもシカも夜行性と思われがちですが、実は明るい時間でも活動します。特に人間の気配が弱い、日の出や日の入り前後は彼らがよく活動する時間帯ですが、周囲が明るいことで電気柵のセンサーが働き、電気が流れていない状態になります。上手く設置した電気柵も、動物が触った時に電気が流れていなければ意味がありません。電気柵は常時通電モードで使用しましょう。
(写真) 電気柵を舗装路に設置してはダメ!

第5回 稲の食べ跡が違うイノシシとシカ!
イノシシとシカが共に生息する地域では、どちらも田んぼに侵入して稲を食べてしまいます。シカは田植え後の苗も食べますが、イノシシは苗をほとんど食べません。乳熟期を迎える頃から両者とも穂についた米を食べ始めます。特にイノシシは、消化の関係から乳熟から糊熟までの固くなっていない米を好んで食べます。また、イノシシは稲を地面に倒して食べることが多く、田んぼは踏み荒らされた様な酷い状態になります。
イノシシとシカでは稲穂の食べ方が異なるため、食べ跡もそれぞれ違ったものになります。イノシシは、穂を口に入れると口を動かして器用に籾米だけを穂から外して食べるため、跡には穂の軸が残ります。シカは、穂を口に入れると鋭利な奥歯で切って食べるため、跡には穂の軸があまり残りません。私の同僚が調査したところ、イノシシだけの被害を受けた田んぼでは、食べられた穂の長さが元の長さの半分以下になることが 14%と少なかったことに対し、シカの被害も受けた田んぼでは、食べられた穂の79%が半分以下の長さになっていました。その内の25%が穂元で切られており、穂が全く残っていない状態でした。
一見、稲が踏み倒された田んぼはイノシシだけの被害と思われがちですが、食べ跡を調べることでシカの被害も発生していることを確認できます。被害がイノシシだけの場合とシカとイノシシどちらもの場合では対策に違いもあるため、食べ跡をしっかり確認してみましょう。
(写真) イノシシとシカの稲の食べ跡。穂の残り方に注目

第6回 イノシシ対策にワイヤーメッシュ柵も有効!
岩手県内では、イノシシやシカの対策として主に電気柵が使われていますが、全国的には金網などを使った物理的に侵入を防ぐ柵も広く普及しています。特に金属製のワイヤーメッシュは強度もあるため、西日本のみならず宮城県や福島県、北陸地方などの積雪地域でも柵の資材として利用されています。岩手県内でも積雪が50cm程度までの地域で設置する場所が平地であれば、ワイヤーメッシュ柵も雪で壊されることが少なく、有効に利用できると思います。
ワイヤーメッシュは長さ2m幅1mで売られているため、柵として設置すると高さが約1mになりますが、イノシシ用であればこの高さで十分です。この高さでは、イノシシがジャンプや乗り越えで柵の上から侵入することはほとんどありません。
イノシシは、ワイヤーメッシュ柵の地際を鼻で押して壊し、そこから潜り込むように侵入します。イノシシがどの程度の重さを鼻で押すことができるかを調査したことがあります。その結果、イノシシは自身の体重と同程度の重さまで鼻で押して動かせることが分かりました。丈夫そうに見えるワイヤーメッシュ柵も、設置状況などによってはイノシシに壊されてしまうことがあります。地面が柔らかい場所やイノシシが頻繁に来る場所では、柵の地際にペグを打って固定したり、ハウスパイプや竹などの長い資材を地際に這わせて柵と固定したりするなどの補強によって、イノシシに壊されにくいワイヤーメッシュ柵になります。
(写真) 全国で普及しているイノシシ用ワイヤーメッシュ柵
第7回 ワイヤーメッシュ柵は格子の大きさにもご注意を!
岩手県内では、ワイヤーメッシュ柵がまだあまり使用されていないためピンとこないかもしれませんが、ワイヤーメッシュの格子の大きさ(網目の大きさ)にはいくつか種類があります。イノシシやシカの被害が増えると、ホームセンターでワイヤーメッシュが売られ始めますが、ほとんどが15cm×15cm格子のものです。15cm格子を柵に使用するといくつかの問題が発生します。
体の小さな生後3ヶ月くらいまでのイノシシの子どもは、格子をすり抜けて侵入してしまいます。子どもだけであればそれほど大きな被害は発生しませんが、子どもの近くには母親のイノシシが必ずいます。母イノシシは、子どもだけが柵の中にいると自分も入りたくなります。そうすると、普通であればイノシシが侵入を諦める強度の柵でも、無理やり壊されてしまう可能性が出てきます。またシカでは、大人のメスであれば15cm格子に簡単に頭を入れることができます。そのまま首の根本付近まで柵の中に入れることもでき、柵沿いの作物を食べられてしまったという事例もあります。このような失敗をしないためにも、イノシシ・シカ対策で使うワイヤーメッシュは、10cmより小さな格子の物を使ってください。
その他にも、裏表に注意する、支柱との結束位置に注意するなど、ワイヤーメッシュ柵を設置する際の注意点はいくつかあります。試しに設置してみたい方は、県や市町村の担当者に相談して侵入防止効果が十分に発揮できるように設置してください。
(写真) イノシシ・シカ対策には10cm以下の格子が適切

第8回 イノシシやシカは意外とジャンプしない
イノシシやシカは、柵を飛び越えるイメージを持たれがちです。しかし、思ったよりジャンプしないことが調査によりわかってきました。
私たちの研究グループでは、イノシシの跳躍力試験を行いましたが、目の前に高さ80cmの柵を置いても、飛び越えるイノシシはいませんでした。低い高さから徐々に上げていく訓練を繰り返して、やっと80cm程を飛び越えました。野外の試験では、ジャンプの得意な個体だけが100cmを飛び越えましたが、それも低い高さから訓練しての結果でした。
シカでも試験を行いました。いきなり高さ100cmを飛び越えたのはオスだけで、メスは越えませんでした。訓練をするとメスも飛び越えるようになり、オス135cm、メス123cmが最高記録でした。野外の試験では、最高記録が140cmでした。
一方で、イノシシやシカが高い柵を飛び越える姿を見たという話もよく聞きます。それには理由があります。イノシシやシカにとって足の怪我は命に直結する一大事です。そのため、柵の中へ侵入する時は怪我をしやすいジャンプをできるだけ避け、柵の隙間から潜り込むなど、安全第一な行動をとります。しかし、人間に見つかった時などは命に関わる緊急事態のため、足の怪我よりも逃げることを優先して柵を飛び越えます。
平地に設置する柵であれば、イノシシで1m、シカで1.6〜1.7m程の高さで飛び込みによる侵入を止めることができます。傾斜地に設置する場合は、動物の目線が上がってしまうので高さを上げて調節してください。
(写真) 柵を飛ぶより潜り込むのが好きなシカ

第9回 無意識に餌付けをしていませんか?
もし皆さんの近所でイノシシやシカに餌付けが行われていたらどう思いますか?実は、全国の集落周辺で人間が無意識に野生動物に対して餌付けをしている状況があります。
奈良公園のシカにせんべいをあげるようなこととは違います。無意識にやっていることなので、まさかこれが餌付けになっているとは、と思うものばかりです。例えば稲の二番穂。早稲品種であれば早ければ8月中旬から稲刈りが始まります。早く刈った稲の切り株から出たヒコバエは生長し、11月ごろには二番穂を出し、条件が良ければ籾に米が実ります。調査をすると、二番穂の米をイノシシやシカが毎晩美味しそうに食べていることが分かりました。同様に、誰も収穫しなくなり放棄された柿なども野生動物の餌になっていることが分かりました。柿はクマで話題になりますが、地面に落ちた実をイノシシやシカがたくさん食べ、時には後ろ足で立ち上がり、枝に付いている実まで食べていることはあまり知られていません。
野生動物にとって冬を乗り切るためにたくさん食べなければならない秋に、長時間餌を探さなくても田んぼで二番穂を、集落で放棄された柿の実を食べれば短時間でお腹いっぱいになれます。イノシシやシカは、自由にたくさん食べられるものが集落周辺にあることに気づき、一年中そこに居着き始め、様々な被害を出してしまいます。近くにいてほしくないイノシシやシカに、皆さんも無意識に餌を与えていないか確認してみましょう。
(写真) 後ろ足で立って柿を探すイノシシ

第10回 ニオイ・音・光の忌避効果は怪しい
ニオイや音、光は手間が掛からず効果があるのではないか?といった相談をよくされます。結論を先に言いますと、ニオイや音、光を使った忌避材や装置をイノシシやシカが嫌うことはありません。
私たちの研究グループでは、忌避効果があるとされているニオイや光、音をイノシシやシカに提示する試験をたくさん行ってきましたが、長期間逃げる、近づかなくなる物はありませんでした。流行りのピンクのテープも、1日〜10日ほどでイノシシもシカもテープを無視して侵入するようになりました。天敵と言われるオオカミの尿は効果があるとして流行しています。もちろんオオカミ尿の試験も行いましたが、イノシシは嫌がるどころか尿を体に擦り付けたりしました。シカも一晩で尿を撒いた場所を無視して餌を食べるようになりました。今のところ、イノシシやシカが本質的に嫌がる物質はありません。
一方で、売られている忌避物質などを使うと、イノシシやシカが来なくなったように感じることがあります。毎日訪れていた農地に、突然いつもと違うニオイや物があると、その環境の変化に対して野生動物は、「何か危険なことが起こるかも」と考えて警戒します。しかし、農地で美味しい物を食べてきたイノシシやシカは、周囲から農地の様子を観察し続け、危険なことはないと判断すると再び侵入してきます。効果があったようでもそれは一時的な警戒であり、イノシシやシカは慣れてしまうと思ってよいでしょう。
(写真) ピンクテープを跨いで入るイノシシ

第11回 イノシシとブタは同じように増えるのか?
イノシシの繁殖に関しては、ブタの情報と混ざって伝わることも多く、注意が必要です。
イノシシは年に1度、4月から6月に母親1頭が平均4~5頭、最大8頭の子ども(ウリボウ)を産みます。しかし、10頭以上のウリボウを見た、イノブタになって10頭以上生むようになった、という話も聞きますが、これは間違いです。
イノシシのメスは、血縁関係のあるメス同士で暮らすこともあります。例えば、メス3頭の群れであれば、1頭あたり子ども4頭を産み、群全体では合計12頭の子どもが生まれることとなります。母親が違っても同じ群れのウリボウ達は、子どもだけで混ざって遊んでいます。その光景を人間が見かけると、まるで1頭の母親が12頭も産んだと勘違いしてしまうでしょう。しかも、母親は警戒心が強く、なかなか人前に姿を見せないため確認することは難しいです。10頭以上のウリボウを見かけたら、間違いなく母親は複数頭いると思ってください。
ブタの様に年に2回出産するイノシシがいる、という話もよく聞きますが、これには原因があります。春の出産に失敗したり、ウリボウが早くに死んでしまった場合、母親の授乳が止まってしまいます。その状態になると母親には発情が戻ってくるため、春から夏に再び交尾をすることがあり、それによって秋にウリボウが生まれます。ですので、イノシシは年に2回出産することはありますが、2回ウリボウを育て上げているわけではないということです。
(写真) ウリボウの模様は3ヶ月くらいで薄くなる

第12回 量より質が重要!被害を減らす捕獲とは?
全国では農作物被害防止を目的とした有害捕獲などでイノシシを約40万頭、シカを約60万頭捕獲しています。しかし、たくさん捕獲しているのに被害が減っていない地域も多くあります。実は捕獲の数よりも、どこでどんな個体を捕まえたかといった捕獲の質が、被害減少に繋がることが分かってきました。
農作物被害を減らすためには、田畑を荒らしている犯人(加害個体)を捕まえなければなりません。すべてのイノシシやシカが犯人だ、と思う方もいるでしょう。実は、被害を与えているのは特定の個体だということが分かっています。
「犯人は現場の近くに潜んでいる」というどこかで聞いた台詞と同じく、加害個体は農地周辺の藪や茂みを生活拠点にしており、山や林の奥にはほとんど移動しません。それとは逆に、農地から離れた場所で生活している個体は、農地に出ることなく暮らしています。イノシシの調査では、農地に現れる個体が、そこから200m以内に生息していることが明らかになりました。シカはまだわからないことも多いですが、イノシシと同様に加害個体は農地周辺からあまり動かないという結果も出ています。このような加害個体の特性から、農地から離れた場所でたくさん捕獲しても被害はあまり減らないということです。
残念ながら、農地から離れた場所で有害捕獲をしている方がまだまだいます。有害捕獲では、たくさん捕獲することを目標とせず、加害個体を上手く捕まえることを意識してください。
(写真) 箱罠の技術も向上させると良いでしょう

問い合わせ先
記事に関する質疑などある場合は、二戸地方農林水産振興協議会(電話:0195-23-9203)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林課
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4854
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
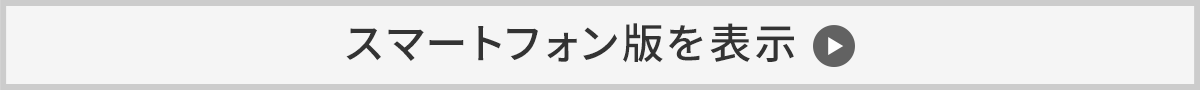






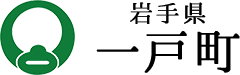
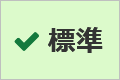





更新日:2025年05月09日