宝永六年銘青面金剛庚申供養塔

県内でも珍しい笠付き角柱型
《町指定有形民俗文化財》
ふりがな:ほうえいろくねんめいしょうめんこんごうこうしんくようとう
名称:宝永六年銘青面金剛庚申供養塔
数量:1
所在地:一戸字北舘
所有者:個人
指定年月日:昭和59年12月25日
庚申(かのえさる)の夜、人が眠りにつくと体内に宿る三尸(さんし)の虫が天に昇り、天帝に宿主の罪業を告げて寿命を縮めようとするので、眠らずにそれを防げば長寿を得られる。
中国の道教に由来する庚申(こうしん)信仰は、平安時代から広がりはじめ、江戸時代には庶民の間で盛んに行われるようになりました。一戸町内でも46基の庚申塔が確認されており、一軒の家に人々が集まり徹夜で過ごす行事が町内各地に広まっていたことがうかがえます。
一戸字北舘の「宝永六年銘青面金剛庚申供養塔」は、約300年前に建立された町内最古の庚申塔です。青面金剛は庚申信仰の本尊とされ、一般的には三つの目と六本の腕を持ち忿怒の表情を浮かべた姿で描かれます。
基壇、塔身、笠の三つの部分からなり、四角柱の塔身正面に「青面金剛庚申供養塔」、裏面に「宝永六年丑十二月廿四日」の文字、向かって左側面に「金剛界五仏」を表す5つの梵字、右側面に「破地獄真言」と呼ばれる密教で用いられる梵字が刻まれています。「破地獄真言」は地獄に落ちて苦しんでいる者を救うための供養で、この庚申塔では本来の長寿延命に加えて、来世の安楽をも願っていることが分かります。
誰がどのように建立したかは不明ですが、付近に修験を伝える吉祥院があったことから密教との関連性が指摘されています。
(注釈)庚申は干支に基づく日付。60日に一度訪れます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 世界遺産課 文化財係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町岩舘字御所野2
電話番号:0195-32-2652
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
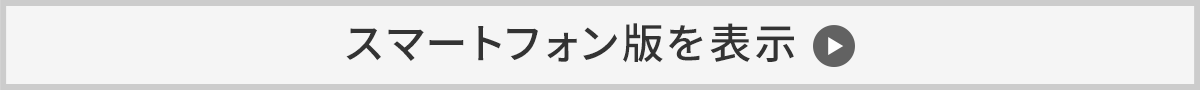






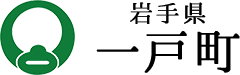
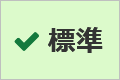




更新日:2021年03月12日